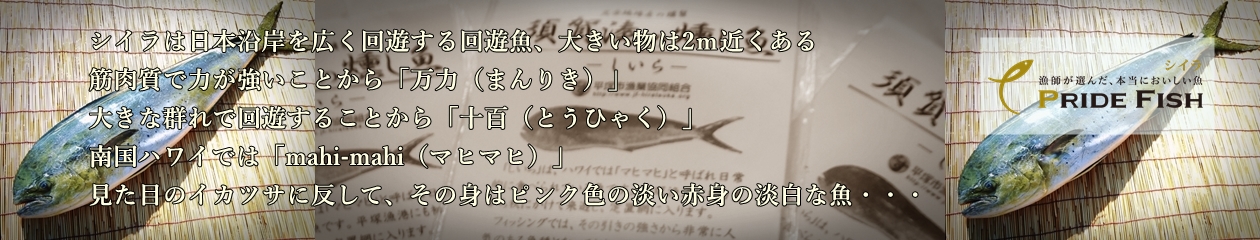2026年1月3日(土)
平塚市では、デジタル庁の進めるデジタルインボイスの取り組みについて、将来的に平塚市内の事業者が導入していくことを想定し、国の目指す姿に対する現状とのギャップを明らかにすることを目的に、実証実験を行っています。【平塚市プレスリリース 2025年12月3日】

これらの仕組みによって、消費者は食品を手に取った際に、二次元コードから手軽に出荷日時や製造者情報を取得できるようになり、デジタル技術を活用した「食の安心」へと繋がります。事業者間では、人を介することなく精算、支払いまで行うことが可能ということで平塚市産業振興課は【Triplo M’s S.A.】の協力の下、アプリ「QMS TRACE」を活用してトレーサビリティ実証実験に山大商事さんと参画しています。
当組合では、2024年度にも同実証実験に参加、地魚の煮付けや地魚燻製にQRコードを貼り付け、食品の足跡をたどっていただきました!

2024年度の取組との違いは、トレーサビリティだけでなく、この記録を利用して製造業者、出荷業者などは、精算の一部まで取り組みます。デジタルインボイスの取組は、ZEDI(全銀EDIシステム)による支払行為まで含めて進められるのが一般的ですが、今回の実証ではZEDIによる支払行為までは行わず、アプリ上での請求手続きまでの実証デジタル技術により、消費者には安心を、事業者には業務効率化を促進します。
当組合と山大商事との間では、日々お魚の水揚げから出荷、受入れ、商品製造が進められています。これらのやり取りが全自動で集計され、精算まで進められるというこで、未来へ進みすぎて追い付けません(笑)が、その一部を体験、体感することで当組合としても一歩先行く技術を理解し、活用をイメージすることができ、業務効率化の糸口となることを期待しています。
消費者の皆様におかれましては、是非、二次元コードを読み取ってみて、いつどこから出荷された商品であるか、どんな商品であるかを覗いてみてください。今回の商品は、【トマ鯖カレー】。山大商事さんにより【道の駅湘南ちがさき(茅ヶ崎市柳島)】に出荷されています。(2025年12月26日より順次)商品に貼り付けされているQRコードを読み取ってトレーサビリティ(商品の足跡)をご確認いただければと思います。2026年2月28日までの期間限定実証実験となります。
※商品が売れて在庫がない場合もございます。なお、同様の商品は、JA湘南あさつゆ広場・JA湘南あふり~な伊勢原・あふり~な比々多・平塚市観光協会みなくる平塚にて販売しておりますが、二次元コードがついているのは、【道の駅湘南ちがさき】のみとなります。
(2025年12月デジタル庁JP PINTに紹介されています)
紹介されている記事はこちら(PDFファイル467KB)