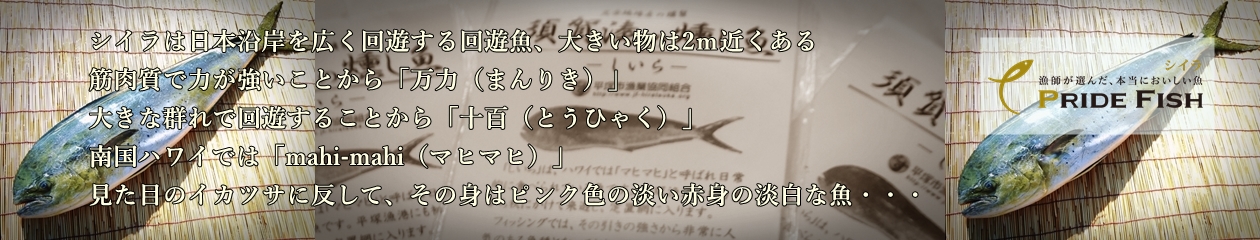2024年4月8日(月)
「かじめ」「あかもく」「こんぶ」「わかめ」を設置しています。4月に入り、そろそろ終了していく海藻たちもあるかなぁ~と思いつつ、漁港の中を覗いてみました。
今回、とても元気な海藻が1つ。それは「あかもく」。県水産技術センターから入手したアカモクの苗。最初は10cm程度でしたが、とんでもないボリュームに成長!
「かじめ」は、残念ながら葉が消失してしまいって、、、寂しい感じに。なんだろなぁ~。。。。「こんぶ」はシーズン終了かな。禍根部分が目立ちました。「わかめ」も葉が固くなったり、葉先がギザギザになって痛んでいる様子。メカブはまだしっかりついていました。


2月との比較をすると差はハッキリしますね。今年、当漁港内では「わかめ」が至る所に生えている様子が確認できました。これは、このプロジェクトで設置したワカメの兄弟たちが増えたのかな?そうだと、こういった取組みも意味があるんだと感じます。

現在元気な、「あかもく」。今回のプロジェクトでは、【ブロック&ロープ&あかもく】をしかけてうまく成長した場合は、そのまま増殖に繋げられるかもとイメージしていました。数個ですがうまく進んだ【あかもくブロック】があったので、漁港内のアカモクそっくり海藻が自生している場所に追加してみました。この「あかもく」が種を落としどんどん増えることを期待します!観察を継続したいと思います。
当組合では、この取り組みは小さな一歩かもしれないけれど、海藻は二酸化炭素を吸収し、地球温暖化解消に役立ってくれているということ、私たちが生活をしている中で二酸化炭素排出と、吸収できるよう取り組みを進めることで、カーボンニュートラルにつながること。そして、海藻が増えればお魚たちの居場所も増え、資源増につながることを期待して取り組みを進めています。

2024年3月16日(土)
たくさんの二酸化炭素を吸収した海藻を収穫体験。地球温暖化解消に少しでも役立ってくれたワカメをたべちゃうイベント、風無し、快晴の素晴らしい天候の中開催することができました。
主催は、着地型観光推進員会(平塚市観光協会内)、運営協力に「たんぽぽミュージックスクール」さんで実施。

まず早速、12月下旬に漁港に設置したワカメを収穫です。ちゃんと育ったかなぁ~と心配でしたが、バッチリでした。獲っても獲っても終わらない~♪数か月ですごく増えるワカメって本当にすごい!

続きまして、コンブも!コンブは11月下旬に設置。最初は、数ミリ程度だったのに!こんなに大きく♪子供たちもコンブ片手に走り回りました(笑)
ちゃんとお勉強も。なぜ漁港で漁師たちが海藻を育てているのか、地球温暖化って?子どもたちそれぞれに受け止めてくれたと思います。

会場は、荷捌き施設に移動して。
今度は、収穫したワカメの試食。色が変わる瞬間や触感、葉・茎・めかぶと3種類食べることができることを実演しました。
エコ楽器の制作を行い、楽器と英語を使ってさわやかに漁港で演奏会。今日の取組みを海外にいる仲間たちへ発信するための動画撮影も行いました。
ブルーカーボン、カーボンニュートラル、サスティナブル、SDGs。いろいろなキーワードがたくさん。大人も子どもも、楽しみながらそれらをより身近に感じ、いっしょに体感・実感できたと思います。海外発信されたら、また報告したいと思います。

2024年3月13日(水)
タマ三郎のブルーカーボンチャレンジ!
今日は、コンブ収穫です。今期、はじめてコンブを導入。どうなるかワクワクドキドキしていたら、、、、、
な、なんと!コンブってこんなに大きくなるんだね~と驚きました。
コンブの産地ではもっと大きく、肉厚だったりすると思いますが、コンブを初めて苗から育てた感想としては、こんなに大きくなる種類でビックリです。あんなに細くかわいかった苗が、どーんと大きくなりました。大きいもので3m近く、幅も20cmはあります。これは感動します。

二酸化炭素をたくさん吸収しながら、大きく育ったコンブはしっかり食べなきゃ!ということで、収穫したコンブを洗って、乾かしました。薄いコンブなので、柔らかく、細かくしてお味噌汁に投入、ワカメ的に使用しても良い感じです。干しているときも、干し終わった後も、とても強い海藻のニオイです。個人的には、おいしいニオイ♪風味豊かです。週末には、イベントがあるのでプレゼントしちゃおうと思います。
🐟平塚市漁業協同組合🐟 次回、開催予定は、4月26日(金)です。 メニュー内「地どれ魚直売会」⬇をご確認ください😀